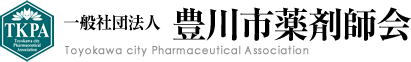健康情報を更新しました「10月10日は、目の愛護デー。目からのSOS気づいてますか?」
今月の健康情報は「10月10日は、目の愛護デー。目からのSOS気づいてますか?」です。
10月10日は、目の愛護デー。目からのSOS気づいてますか?
現代の私たちの暮らしに、欠かせないスマホやパソコン。
仕事やプライベートで1日の大半はデジタルデバイスに触れている方も多くいらっしゃると思います。
これらは便利な一方、長時間使用することで目に疲れを感じ負担がかかってしまうことも。
10月10日の目の愛護デーにちなんで、今回は目の健康についてご案内いたします。
目を長時間使う作業を続けることで、目だけでなく体全体に症状がでることがあります。
休息や睡眠をとっても十分に回復しない状態が続くときは眼精疲労になっているかもしれません。
ピントを調節する毛様体筋は自律神経によって支配されています。
目を酷使していると、毛様体筋が疲れて自律神経のバランスが崩れ、全身に症状があらわれると考えられています。
スマホやタブレット、パソコンなどを長時間使用すると、目の乾燥や疲れ、頭痛などの症状があらわれやすくなります。
目を一点に集中させたままの作業や読書は、目の筋肉を長時間同じ位置に固定することになり、目の疲れやドライアイの症状をもたらすことがあります。
明るすぎる照明や暗すぎる照明は、目に負担をかけることがあります。
特に長時間の間接照明や蛍光灯の下での作業は、目の疲れを感じやすくなります。
空調の効いた場所や乾燥した環境では、目の表面が乾燥しやすくなります。
それに伴い、目の疲れや不快感が生じることがあります。
ストレスは体内の免疫系や自律神経に悪影響を及ぼし、目の症状を悪化させる可能性があります。
仕事や学業、家庭の問題など、日常生活のストレスを軽減することは、目の健康にとっても重要です。
1.スマホの画面液晶の明るさを調整する
2.スマホやパソコンを使用する際は、目を近づけすぎない
3.デジタルデバイスの長時間使用時は休憩を入れる(1時間毎に10分程度)
4.メガネやコンタクトの度数を合わせる
目は視覚を感じるとても重要な働きがあります。
目のケア方法をためしてみて、目を労わる生活を心がけましょう。
提供:レイヤード
健康情報を更新しました「9月18日は敬老の日、健康寿命について」
今月の健康情報は「9月18日は敬老の日、健康寿命について」です。
9月18日は敬老の日、健康寿命について
毎年9月の第3月曜日は敬老の日ですね。
現在、日本は超高齢社会と言われています。
2022年時点で65歳以上の高齢者は3627万人に増え、過去最多となりました。
総人口は減少傾向にある一方で、高齢者人口はまだ増加しつづけると考えられています。
こうした中、寿命を延ばすだけでなく「健康的に生活できる期間」をいかに延ばすかが課題になっています。
今回は敬老の日にちなんで、健康寿命についてご案内します。
健康寿命は2020年にWHO(世界保健機構)によって提唱されました。
平均寿命と健康寿命は、人々の健康と長生きに関する指標です。
一般的な人々の平均的な寿命を表し、日本では男性が81.41歳、女性が87.45歳と報告されています。
「病気や障害のない健康な状態で過ごせる期間」を指します。
平均寿命と健康寿命の差が縮まるほど、健康的に長く生きられると考えられています。
2019年時点で平均寿命と健康寿命の差は男性が約8年、女性が約12年となっていますので、約10年は健康に何らかの不安がある状態といえます。
この差を縮めるためには、日々の健康習慣が大切です。
腹八分目を心がけ、規則正しく1日3回食べましょう。緑黄色野菜、魚、肉、卵をバランスよく摂取しましょう。
加齢に伴い筋力や筋肉量、身体機能が低下します。
週に2日以上30分の運動習慣で、持久力や筋力の向上を目指しましょう。
加齢に伴い睡眠が短くなったり、浅くなったりして、夜中に何度も目が覚めてしまうようになり睡眠の質が低下してしまいます。
昼寝を30分以上しない、寝るときは日の光を遮断する、朝の光を浴びる、日中は適度な運動を心がけましょう。
高齢者の受療率をみると循環器系の疾患や筋骨格系の疾患の割合が高い傾向にあります。
循環器疾患である、高血圧症は生活習慣病の1つです。
健康寿命を延ばすためには、定期的な健康診断で生活習慣病の重症化を防ぎましょう。
また自治体によって、健康診断や予防接種が公費で受けられる場合があります。
長寿大国の日本、「健康に長生きしたい」は私たちの願いです。
将来の自分のために健康習慣を意識して生活しましょう。
健康に不安がある方、今の健康状態を知りたい方は一度医療機関へご相談ください。
出展:
厚生労働省「健康寿命の令和元年血について」、「平均寿命と健康寿命をみる0416」、「令和3年簡易生命表について 」
提供:レイヤード
健康情報を更新しました「健康習慣「旬の夏野菜」を食べよう」
今月の健康情報は「健康習慣「旬の夏野菜」を食べよう」です。
健康習慣「旬の夏野菜」を食べよう
うだるような暑い日々。
暑さで食欲が低下したり、疲労がたまっていたりしていませんか?
夏を元気に過ごすためには、栄養をしっかり摂ることが大切です。
旬の夏野菜には、ビタミンやミネラルが豊富に含まれており、疲労回復や食欲増進などの効果があります。
今回は夏野菜の栄養素と効果についてご案内します。
きゅうりは約95%が水分で、体を冷やしてくれます。
疲労回復やむくみ改善の効果もあります。
●カリウム
●ビタミンC
●食物繊維
疲労回復や貧血防止の効果が期待できます。アミノ酸の一種のメチオニンはアルコールの分解を促す効果があります。
●たんぱく質
●ビタミンB群
●ビタミンC
●食物繊維
●メチオニン
トマトの赤色成分のリコピンは抗酸化作用、老化防止やがん予防の効果があります。
また美肌効果、むくみ改善など美容に適した野菜です。
●ビタミンA
●ビタミンC
●ビタミンE
●カリウム
●β-カロテン
オクラのネバネバのもとになるペクチンは腸内環境を整えてくれる作用があります。
骨や歯の形成を助け、貧血の予防にも効果があります。
●β-カロテン
●葉酸
●カリウム
●カルシウム
●食物繊維
ゴーヤの独特の苦みが胃液の分泌を促して食欲増進の効果があり、ビタミンCで夏バテを防止します。
●食物繊維
●カルシウム
●ビタミンC
体を動かすエネルギーになる炭水化物や、筋肉や皮膚をつくるたんぱく質が豊富に含まれています。
そのほか、皮膚や髪の毛の健康維持の効果が期待できます。
●ビタミンB群
●ビタミンC
●食物繊維
●カルシウム
ピーマンのビタミンCは、レモンの約1.5倍含まれています。
抗酸化作用で風邪予防やシミ・シワを予防し、美肌づくりの効果が期待できます。
またピーマンの香り成分のピラジンは血液をサラサラにする効果もあり、心筋梗塞や脳梗塞の予防効果もあります。
●ビタミンA
●ビタミンC
●β-カロテン
約90%は水分のナス。お腹の調子を整えてくれます。
抗酸化作用のあるポリフェノールが含まれているため、生活習慣病の予防にも効果的です。
●ポリフェノール
●食物繊維
●カリウム
●葉酸
夏野菜は、その時期に必要な栄養が摂れて、暑さでほてった体を冷やす作用もあります。
積極的に取り入れて、夏を乗り切りましょう。
提供:レイヤード
健康情報を更新しました「腸に良い事をしよう「腸活のススメ」」
今月の健康情報は「腸に良い事をしよう「腸活のススメ」」です。
腸に良い事をしよう「腸活のススメ」
皆さんは腸内にどのくらいの腸内細菌がいるかご存じですか?
その数、100兆個。種類として1000種類の菌が腸内に生息しています。
腸は未だ不明の部分が多い臓器ですが、腸の不調はうつ症状などのメンタル面にも影響が出ることが分かってきました。
今回は腸内バランスを保つ「腸活のススメ」についてご案内します。
腸内細菌は、「日和見菌」「善玉菌」「悪玉菌」の3種類に分けられます。
最も多いのは「日和見菌」で全体の7割を占めます。
続いて「善玉菌」が2割で「悪玉菌」が1割です。
健康な腸内は、善玉菌が悪玉菌の増殖を防いで腸内環境が保たれています。
バランスが乱れ悪玉菌の割合が増えると、普段は害のない日和見菌も悪玉菌と同じように悪い働きをはじめます。
そうして腸内環境が悪化し、体に様々な影響がでます。
●かぜ・感染症
●肥満
●糖尿病
●動脈硬化症
●炎症性腸疾患
●大腸がん など
たんぱく質・脂質が中心の食生活、ストレス、過労、運動不足が原因です。
また、うつの患者さんには下痢や便秘が多いということも報告されています。
腸の状態は、ストレスや緊張にも影響されるので心と体は密接に関係していることがわかります。
善玉菌は、腸内を酸性にして悪玉菌の増殖を抑える作用があります。
ビフィズス菌や乳酸菌は、善玉菌の1種で腸内環境を健康的に整えるので積極的にとりましょう。
方法は2つあります。
生きた善玉菌の「プロバイオティクス」を直接とる方法と、いまある善玉菌を増やす「プレバイオティクス」をとる方法です。
ヨーグルト・乳酸菌飲料・納豆・キムチ・漬物などの食品から摂取。
大豆・たまねぎ・ごぼう・アスパラガス・バナナ・豆類などを摂取。
善玉菌の餌である「食物繊維」「オリゴ糖」をとることで、腸にすでにある善玉菌を増やす目的があります。
キムチや漬物は塩分濃度も高いので、バランスよく食べることが大切です。
また、生きた善玉菌はせっかくとっても腸内に行くまでに胃酸にやられてほとんど死滅してしまいます。
定期的に一定量を摂って腸に届け続けることが大切です。
腸はセロトニンという幸せホルモンが作られる場所でもあります。
心身ともに健康になるよう、「腸活」をしてみてください。
提供:レイヤード
健康情報を更新しました「強さは真夏並み!梅雨時期の紫外線」
今月の健康情報は「強さは真夏並み!梅雨時期の紫外線」です。
強さは真夏並み!梅雨時期の紫外線
新緑の季節を迎え、徐々にテレビCMやドラッグストアでも日焼け止めをよく目にするようになり、紫外線対策を気にし始める方もいらっしゃると思います。
曇天・雨天の多いこの季節、紫外線の「量」はピークである真夏に比べて少ないものの「強さ」は真夏並みと言われています。身近なようで、実は知らないことの多い紫外線について健康への影響という観点でみていきましょう。
紫外線は私たちの目には見えませんが、太陽光(日射)の一部であり、基本的な性質は可視光線と同じです。
季節や時刻、天候などにより紫外線の絶対量や日射量に占める割合は変化しますが、可視光線と同じように、建物や衣類などでその大部分が遮断されます。
一方、日中は日陰でも明るいように、大気中での散乱も相当に大きいことがわかっています。
中でも、人体に有害といわれているUV-Bは散乱光の占める割合が高くなっています。
紫外線は、私たちがカルシウムを代謝する際に重要な役割を果たすビタミンDを皮膚で合成するために必要です。
紫外線を浴びすぎた場合には日焼け、しわ、シミ等の原因となるほか、長年浴び続けていると良性/悪性の腫瘍や白内障等を引き起こすことがあります。
最適な紫外線量には個人差がありますが、正しい知識を持ち、紫外線の浴びすぎに注意しながら上手に紫外線とつきあっていくことが大切です。
ビタミンDの観点からは短時間の日光浴は必要ですが、一方で紫外線には発がん作用などの好ましくない作用があります。
適切な量というのは、地域や季節、時刻、天候、服装、皮膚色(スキンタイプ)など多くの要因で左右されるため、一律に表現できませんが、1日に必要な日光照射時間は夏に15〜30分程度と言われています。
紫外線の強さは、時刻や季節、さらに天候、オゾン量によって大きく変わります。
同じ気象条件の場合、太陽が頭上にくるほど強い紫外線が届きます。
一日のうちでは正午ごろ、日本の季節では6月から8月に最も紫外線が強くなります。
状況に応じて以下の対策を活用しましょう。
1.紫外線の強い時間帯を避けて外出する。
2.日陰を利用する。
3.日傘を使う、帽子をかぶる。
4.衣服で覆う。
5.サングラスをかける。
6.日焼け止めを上手に使う。
よく聞くし、なんとなく意識したことがある紫外線対策ですが、いかがでしたか?
紫外線と上手に付き合いながら、梅雨時期、そして夏を楽しく元気に過ごしましょう。
提供:レイヤード
健康情報を更新しました「血圧が上がりにくい生活習慣」
今月の健康情報は「血圧が上がりにくい生活習慣」です。
血圧が上がりにくい生活習慣
5月17日は世界高血圧デーです。
生活習慣病のリスク要因となっている高血圧。
現在、20歳以上の日本人の2人に1人が高血圧といわれています。
自覚症状があまりなく、気づいたころには血管がもろくなっていた、なんてことも。
さらに、動脈硬化や心筋梗塞などといった合併症を引き起こす場合があります。
放置してしまうと危険な高血圧ですが、生活習慣を改善することで予防することができます。
今回は高血圧になりにくい生活習慣をご案内いたします。
心臓のポンプにより血管に血液が流れるとき、内側からかかる圧力を「血圧」といいます。
遺伝的要素もありますが、一番は塩分過多な食生活です。
塩分を摂りすぎると体内の水分が増え、血液量も増えます。
増えた血液を早く排せつさせようと圧がかかり、血圧が上がるのです。
日本人は食塩の摂取量が多いため血圧が上がりやすいといわれています。
また、肥満、運動不足などの生活習慣も要因です。
健康のための塩分摂取量の目標値は男性が7.5g未満、女性が6.5g未満 (厚生労働省「2020年版日本人の食事摂取基準」)です。
カップ麺を1つ食べることで、1日の目標量のほとんどを占めてしまいます。
| 食品名 | 塩分 |
|---|---|
| カップ麺 | 5.5g |
| インスタントラーメン | 5.4g |
| 梅干し | 1.8g |
| 塩サバ | 1.1g |
| 食パン(6枚切り)1枚半 | 1.2g |
参考:消費者庁「栄養成分表示を活用しよう④減塩社会への道」
1番効果があるのは食生活の改善です。
●漬物は浅漬けにする
●麺の汁は飲まない
●外食や加工食品を控える
●具だくさんの味噌汁
●酢・ケチャップ・マヨネーズ・ドレッシング・香辛料などの調味料を使用
またカリウムは、塩分であるナトリウムを排泄する働きがあります。
カリウムは野菜や果物に多く含まれるため、積極的な摂取が望ましいと考えられます。
一度に塩分を無くす生活は負担に感じると思います。
まず普段の生活のなかで、すこしだけ塩分を気にして生活してみることからはじめてみましょう。
未来の自分が健康でいられるためには、いまの生活習慣が大切です。
参考:厚生労働省e-ヘルスネット
提供:レイヤード
健康情報を更新しました「放置は危険!健康診断の「要再検査」や「要精密検査」」
今月の健康情報は「放置は危険!健康診断の「要再検査」や「要精密検査」」です。
放置は危険!健康診断の「要再検査」や「要精密検査」
健康診断で「要再検査」や「要精密検査」の結果が出ても、放置している人は多いのではないでしょうか?
「症状がないから」「いつものことだから」と甘くみていると、気づかないうちに病気を進行させてしまう危険もあります。
今月は、健康診断で引っかかりやすい項目、「要再検査」や「要精密検査」の意味、危険性などについて解説します。
健康診断には様々な検査項目がありますが、特に基準値をはずれやすい項目は4つあります。
●コレステロール値(脂質)
●血圧
●肝機能
●血糖値
どの項目も生活習慣病に関連しています。
生活習慣病は自覚症状が少なく、気づかないちに糖尿病、脳卒中、動脈硬化、心筋梗塞など、深刻な病気に移行する可能性があります。
健康診断で引っかかった場合は、早めに医療機関を受診するようにしましょう。
健康診断の結果は、「異常なし」「要経過観察」「要再検査」「要精密検査」「要治療」などの判定区分に分かれます。
項目の測定数値が正常の範囲内で、心配な所見が認められませんでした。
前日の食事や当日の体調で引っかかることもあります。
健康診断の結果が、たまたまなのか、病気のサインなのかを判断するための要再検査です。
緊急性がないこと多いですが、注意が必要ですので医療機関への受診、生活習慣の改善を心がけましょう。
特定が難しい病気が疑われる場合にさらに詳しい検査を必要とする状態です。
病気があると断定しているものではありませんが、身体に何らかのトラブルが発生している可能性があります。
なるべく早めに精密検査を受けましょう。
すぐに治療が必要な状態です。早急に専門の医療機関を受診しましょう。
上記の中で、一般的に再検査が必要になるのが、「要再検査」「要精密検査」です。
「要再検査」の場合は、生活習慣の改善や再検査の受診、「要精密検査」の場合は、必ず再検査を受診するようにしましょう。
要再検査、要精密検査ともに、必ずしも病気があるというわけではありません。
再検査の結果何も異常がないこともありますが、異常がないことを確認することも再検査の重要な役割です。
いかがでしょうか?
再検査自体、義務ではなく任意ですので、放置されている人も多いことでしょう。
しかし、病気を進行させてしまった場合、身体への負担はもちろん、経済的な負担も大きくなってしまいます。
ご自身の体と心の健康のために、健康診断の結果は放置せず、生活習慣の改善、再検査の受診など必ず行動するようにしましょう。
提供:レイヤード
健康情報を更新しました「女性に多い「骨粗しょう症」について」
今月の健康情報は「女性に多い「骨粗しょう症」について」です。
女性に多い「骨粗しょう症」について
毎年3/1~3/8は「女性の健康週間」です。
年齢とともに変化する女性ホルモン。
ホルモンの変化は体調だけでなく「骨」にも影響があります。
今月は女性の健康「骨粗しょう症」の原因や予防法などをご案内いたします。
骨密度が低下し、骨がもろくなる病気です。
尻もち程度に軽く転んでも骨折するリスクが高まります。
足の太ももの付け根や背中を骨折してしまうと、歩行が困難になりそのまま寝たきりになる恐れがあります。
ほとんどは自覚症状がなく、骨折したときに発覚しやすいのが特徴です。
20代のころに比べて背中が丸くなったり、身長が3㎝以上縮んだりしている方は要注意。
気づかないうちに、背骨がつぶれ「圧迫骨折」を起こしている可能性があります。
1.栄養不足(骨を形成するカルシウムやビタミンD、マグネシウム)
2.運動不足
3.加齢
4.遺伝的要素
5.閉経後のホルモンバランスの変化
女性ホルモンである「エストロゲン」が関係しています。
「エストロゲン」は骨を形成する細胞に必要な作用があり、閉経後に急激に減少していきます。
減少すると骨形成の代謝バランスが崩れ、骨粗しょう症のリスクが高まります。
女性よりは少ないものの、男性でも加齢に伴い骨量が減少していくので予防が大切です。
カルシウムやビタミン類をバランスよく摂りましょう。
●カルシウム:乳製品、骨ごと食べる小魚、干しエビなど
●ビタミンD:鮭、鶏卵、干しシイタケなど
●ビタミンK:ほうれん草、小松菜、ニラなど緑色野菜
エストロゲンと似た働きをする「イソフラボン」は大豆製品を摂ることでエストロゲンの減少を補ってくれます。
運動の刺激で骨の中の細胞が活発化されます。
骨を強くする効果がありますのでウォーキングなど運動を習慣にすると良いでしょう。
骨粗しょう症は加齢や遺伝などが関係することから生活習慣を正すだけでは防げません。
50歳すぎたら定期的に骨密度検査を受けましょう。
自分の骨の状態を知ることで、健康寿命を延ばしましょう!
提供:レイヤード
健康情報を更新しました「冬にご注意!ヒートショック・低温やけど・窒息事故」
今月の健康情報は「冬にご注意!ヒートショック・低温やけど・窒息事故」です。
冬にご注意!ヒートショック・低温やけど・窒息事故
冬は外と室内の寒暖差に体が追いつけなかったり
暖房器具によって思わぬ事故を起こす可能性があります。
今月は冬に注意してほしい怪我や事故、予防策や対処法をご紹介いたします。
寒暖差によって血圧が大きく変動することで、心筋梗塞、失神、脳梗塞などを引き起こします。
特に入浴時に起こりやすく、溺死や急死につながる恐れがあります。
1.入浴前に脱衣所は暖房器具で温めましょう。
2.熱いシャワーを流し、蒸気で浴室全体を暖めましょう。
3.お湯の温度は41度以下で10分程度で上がりましょう。
●浴室内で起きたら、お湯を抜いてすぐ引き上げます。
●意識がない場合は救急車を呼び、呼吸がなければ救急車到着まで胸骨圧迫を続けます。
●意識があっても何か症状がある場合はすぐ救急車を呼んでください。
低温やけどとは少し熱いと感じる温度(44℃~50℃)を長時間、肌に直接触れさせることでじわじわと皮膚の奥まで損傷するやけどのことです。
就寝中の湯たんぽ、電気毛布、ホットカーペットや、使い捨てカイロなどが原因で起こります。
自覚がない方が多く、実際の見た目よりも重傷の場合があります。
1.電気毛布や湯たんぽは就寝前に使用し、就寝時の使用を控えましょう。
2.ホットカーペットはタイマーのセットをして長時間の使用を避けましょう。
3.熱源は肌に直接触れないようにしましょう。
●すぐ水道水などの流水で患部を20分程度冷やします。
●水ぶくれ(水疱)ができたら潰さずそのままにしてください。
●軽いやけどに見えても肌の奥まで損傷している場合があります。すみやかに医療機関へ受診してください。
お正月に余ったお餅や、節分の豆を食べるときに窒息事故が起きやすくなります。
よく噛まずに食べる人、小さいお子さんや高齢者の方は十分に注意しましょう。
1.一口サイズに切りましょう。
2.ゆっくりとよく噛む習慣をつけましょう。
3.飲み込む前に次の食品は口にいれず、一口ずつ食べましょう。
●意識がある場合は可能な限り咳をさせましょう。
●呼吸が出来ない状態の場合、すぐに救急車を手配しましょう。
●応急措置として傷病者の頭を低くし、手の付け根で傷病者の肩甲骨の間を力強く何度も連続してたたく背部叩打法(はいぶこうだほう)を行いましょう。
冬の事故は思わぬところからやってきます。
しっかり予防して寒い冬を乗り越えましょう。
提供:レイヤード
健康情報を更新しました「子供も冷えている!?冷えの原因と対処法」
今月の健康情報は「子供も冷えている!?冷えの原因と対処法」です。
子供も冷えている!?冷えの原因と対処法
厳しい寒さに、体の冷えを感じやすいこの時期。
「冷えは万病の元」という言葉があるように、体が冷えると様々な不調をもたらします。
体の冷えを訴えるのは大人だけではありません。
体温が高いといわれている子供でも平熱が35度~36度前半くらいの低い子もいます。
今回は冷えによる不調や原因、改善策などご紹介いたします。
体温が36.5度以上で血中の免疫細胞が活発化するといわれています。
免疫細胞はウイルスが体内に侵入すると攻撃してくれる働きがあります。
逆に体温が低いと免疫力が低下し血流も悪くなるので、体の不調へとつながりやすくなります。
●肩こり、腰痛
●イライラ、不眠
●風邪をひきやすい
●代謝が落ちて太りやすくなる
●月経不順、月経痛
●白髪、薄毛
●肌荒れ
●低血圧
運動不足で筋肉量が少ないと体はうまく体温を上げられず冷えやすくなります。
家遊びが好きなお子さん、椅子に長時間座っていることが多い受験生、筋肉量が少ない女性や高齢者
ストレスや不規則な生活などで自律神経が乱れると、体温調節がうまく機能せず冷えやすくなります。
20代~40代の女性や高齢者
冷たい飲み物など体を冷やすものをとり過ぎると胃腸などの内臓機能が冷えやすくなります。
男女問わず全年代
1. 38度~40度のぬるめの湯舟に長く入る
2. 暖かい飲み物(ウーロン茶、紅茶)を飲む
3. ストレッチ、ウォーキングなど軽い運動をする
4. マフラー、腹巻、靴下で首、お腹、足首を温める
5. 冬野菜など旬な食材は体を温める効果があるので料理に取り入れる
6. 体温調節機能を育てるため、室温を温めすぎない(冬は16度~18度が最適)
冬は感染症も増える時期です。
平熱が低い方は体を冷やさないように注意して体の免疫力を高めましょう。
提供:レイヤード