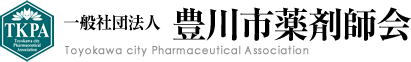健康情報を更新しました「長引く咳に潜む病気のサインとは!?」
今月の健康情報は「長引く咳に潜む病気のサインとは!?」です。
長引く咳に潜む病気のサインとは!?
師走に入り本格的に寒くなってきました。
皆さんは風邪の代表的な症状というと何を想像されますか?
「咳、熱、鼻水、のどの痛み」などを想像する方が多くいらっしゃると思います。風邪症状の1つである「咳」。
その「咳」が3週間以上続くとき、もしかしたら風邪ではない別の病気が潜んでる可能性があります。
一般的な風邪は80~90%がウイルス、残り10%が細菌感染が原因です。
どちらも自己免疫や適切な治療をすることで1~3週間以内に症状は回復していきます。
3週間以上にわたり長引く咳の原因は、主に「咳ぜんそく」「アトピー咳嗽(がいそう)」「胃食道逆流症」「副鼻腔気管支症候群」の4つに多い傾向です。
風邪、ストレス、花粉など様々なきっかけで発症します。
気管支ぜんそくへと移行すると完治が難しいので早めの治療が必要です。
【症状・傾向】
●痰を伴わない乾いた咳
●就寝前~明け方に咳込む
●冷気、電車乗車時、ホコリ、香水など少しの刺激に敏感に反応
●喘鳴(ヒューヒュー、ゼイゼイ)や、呼吸困難はない
●風邪薬が効かない
気管に異物混入を防ぐ「防御反応」が過剰になり、少しの刺激にも敏感に反応して咳が出ます。
咳ぜんそくと症状が似ていますが、風邪薬、咳ぜんそくの薬は効果がありません。
【症状・傾向】
●痰を伴わない乾いた咳
●就寝前~明け方に咳込む
●冷気、電車乗車時、ホコリ、香水など少しの刺激に敏感に反応
●喘鳴(ヒューヒュー、ゼイゼイ)や、呼吸困難はない
●のどのかゆみやイガイガがある
●アレルギー性疾患の既往歴やご家族にいる方が罹りやすい
逆流した胃液がのどや気管支を直接刺激したり、食道の粘膜を通して神経を刺激したりすることで反射的に咳が出ます。
【症状】
●のどの痛み
●胸やけ
●呑酸
鼻と気管支の両方が炎症することで発症します。口呼吸が多くなるため、気管支炎を誘発することもあります。
【症状】
●痰がからんだ湿った咳
●黄色~緑色で粘り気のある痰が出る
●鼻づまり、鼻汁、嗅覚障害などの症状がある
●喘鳴(ヒューヒュー、ゼイゼイ)や、呼吸困難はない
この他、喫煙による慢性閉塞性肺疾患(COPD)、百日咳、マイコプラズマ感染、クラミジア肺炎が原因で咳が長引くことがあります。
咳が長引くほど、生活の質(QOL)は下っていきます。
当てはまる症状がある方は一度医療機関へ受診しましょう。
提供:レイヤード
健康情報を更新しました「季節性うつ病」
今月の健康情報は季節性うつ病」です。
季節性うつ病
11月、朝の冷え込みにだんだんと冬の気配を感じるようになりました。
日の入りが早くなっていき、夜が長く感じるこの時期。
なんとなく気分が沈む、疲れやすいなど鬱々とした気分でお悩みではありませんか?
その症状、長く続くようなら「季節性うつ病」かもしれません。
季節の変わり目、日照時間が短くなる時期に発症するうつ病です。
正式には季節性感情障害(SAD)といい、10月~11月から症状が出て3月ごろに回復します。秋になるとまた発症し、毎年繰り返すのが特徴です。
一般的な「うつ」と似ている症状
●疲れやすく、動くのがおっくう
●気分が落ち込む
●以前のように仕事をこなせない
●今まで楽しめていたことも楽しいと思えない
上記の症状に加えて季節性うつ病の特徴的な症状
●過食や食欲減退
●日常生活に支障が出るほどの過眠
秋冬は日照時間が短く、日光を浴びる時間が少なくなることが季節性うつ病の一因です。人間は日光を浴びると脳内でセロトニンが分泌されます。
セロトニンはストレス軽減や精神の安定、脳の活発化などに効果がある物質です。また、自然な眠りを誘う作用のあるメラトニンをつくる材料でもあります。
メラトニンの分泌不足で、睡眠リズムや体内時計が乱れるのも、うつ発症の起因となる可能性があります。
季節性うつ病は生活習慣を改めることにより症状を緩和することができます。
日光浴に加えウォーキングでもセロトニンが分泌されます。
午前中に15分~30分程度、散歩してみましょう。
自然の光が理想ですが、照明を明るくすると体内時計を調整してくれる効果があります。日当たりがいい窓辺で仕事するのも良いでしょう。
睡眠時間が不規則だと体内時計が乱れます。早寝早起きを心がけましょう。
セロトニンを作るには食事から摂れる栄養が必要です。
肉、魚、卵、大豆、緑黄色野菜、フルーツなどバランスよく食べましょう。
毎年繰り返す症状なので少しでも改善できるよう、まずは日光浴から初めてみましょう。症状が重い方は医療機関へご相談ください。
提供:レイヤード
健康情報を更新しました「飽食な時代に!? 今増えている「新型栄養失調」」
今月の健康情報は「飽食な時代に!? 今増えている「新型栄養失調」」です。
飽食な時代に!? 今増えている「新型栄養失調」
食べ物に溢れた現代。
食品ロスが社会問題となり、食糧困難とは程遠い時代といえる今、「栄養失調」になる人がいます。
いったい何故でしょうか。
今回は飽食な時代の“新型栄養失調”についてご案内していきます。
栄養失調といえば、充分な食事をとれずやせ細った人をイメージする方もいらっしゃると思います。
新型栄養失調は、摂取カロリーは足りているのに、食生活の偏りなどで必要な栄養素が不足している状態のことです。
例えば肥満の方でも、脂質や糖質ばかり摂り、たんぱく質など必要な栄養が不足すると、体は低栄養になってしまいます。
低栄養は、自由に食事を選べる時代こそ注意が必要です。
| 原因 | 栄養が不足しやすいもの | |
|---|---|---|
| 20代女性 | ・食事制限のダイエット ・間食が多く不規則な食生活 ・ファストフードの偏り |
炭水化物、たんぱく質、ビタミンA・B1・D、カルシウム、亜鉛、鉄 |
| 40~50代の男性 | ・外食が多い ・食事はカップ麵で済ませる ・炭水化物の摂取が多くカロリー過多 |
たんぱく質、ビタミンA・C、食物繊維、カルシウム、鉄、亜鉛 |
| 高齢者 | ・食欲が出ず、食事量が減る ・嚙む力が弱く肉や魚を食べない傾向 |
たんぱく質、カルシウム、ビタミンD、食物繊維 |
だるさ、疲労感、気分の落ち込み、便秘、肌荒れ、貧血、免疫力の低下、片頭痛、冷え性
1日3食、栄養バランスのとれた食生活が理想ですが、毎日続けるのは、すこし負担に感じるかもしれません。
忙しい方にはコンビニごはんでも手軽に栄養をとれます。
たんぱく質…鶏のからあげ、豚の生姜焼き
炭水化物…おにぎり、うどん、バナナ
ビタミンA…シソおにぎり、海苔巻き、レバニラ
ビタミンB1…豚の生姜焼き、枝豆、サラダチキン
ビタミンB2…レバニラ、納豆
カルシウム…しらすおにぎり、ヨーグルト、チーズ
鉄…豆とひじきのサラダ、梅ひじきおにぎり
亜鉛…チーズちくわ、ゆで卵、卵マカロニサラダ
健康的な生活には「栄養」が不可欠です。
栄養バランスを整え、心身共に本当の健康を手に入れましょう。
提供:レイヤード
健康情報を更新しました「救急医療週間 正しく知ろう“AED”について」
今月の健康情報は「マスク生活で隠れ酸欠になっている!?」です。
救急医療週間 正しく知ろう“AED”について
9月9日は救急の日、9日を含む1週間(日曜~土曜)は救急医療週間です。 今回は救急医療の現場で使用される“AED”についてご案内していきます。
“AED”は心停止状態となった心臓に強い電流(電気ショック)を与えることで、心臓の動きを取り戻す医療機器です。
心臓による突然死の多くは「心室細動」が原因とされています。
「心室細動」は、心臓がけいれんして血液を送るポンプ機能が正常に機能しなくなる不整脈です。
発症して処置されないままだと約5分で死に至ります。
救急車が到着するまで約8分を要するので“AED”の処置がとても重要になります。
“AED”は駅や公共施設などに設置されていて、一般の方にも使用できます。
① 反応の有無を確認します。周辺の人に救急車要請や、“AED”を探すよう呼びかけてください。
② 呼吸が無ければ“AED”到着まで胸骨圧迫(心臓マッサージ)を行います。
③ “AED”が到着したら、救急車到着まで胸骨圧迫と併用してください。
使い方は シンプルな3STEPです。
1. “AED”のフタを開けると、自動的に電源がONになり音声が流れます。
2. 音声ガイドや画面の指示に従い電極パッドを所定の位置に貼ります。
3. 電気ショックのボタンを押してください。
※AEDの機種によっては手動で電源を入れます。
未就学児用モードに切り替えて実行してください。
2枚のパッド同士が接触しないように胸と背中にパッドを貼り付けてください。
・ペースメーカーを植え込んでいる場合は、ペースメーカーより8㎝以上離して電極パッドを貼ります。
・介助者が感電することがあるので、倒れている場所が濡れている場合は乾燥した場所に移動しましょう。また、傷病者の体が汗や水で濡れている場合は拭いてください。
電極パッドを貼ると、自動で心電図を解析してくれます。
電気ショックの指示が出ますので迷うことなく使用してください。
“AED”は地域の消防局などで講習会を実施しています。
ぜひ参加して、正しい知識と技術を身につけましょう。
提供:レイヤード
健康情報を更新しました「マスク生活で隠れ酸欠になっている!?」
今月の健康情報は「マスク生活で隠れ酸欠になっている!?」です。
マスク生活で隠れ酸欠になっている!?
新型コロナウイルスの流行が続いており、マスクは生活に欠かせないものとなりました。
そんな中、頭痛や体調不良を感じる人もいらっしゃるのではないでしょうか。
もしかしたらその不調、マスクによる酸素不足が原因かもしれません。
今回は、気づかないうちに酸欠状態になっている「隠れ酸欠」についてご紹介いたします。
1つはマスク着用時の“口呼吸”といわれています。
“口呼吸”は“鼻呼吸”より取り込む酸素の量が少なく、充分に酸素を取り込めません。
2つ目は、“二酸化炭素過多”です。
マスク着用時に自分が吐いた空気を吸うことで、二酸化炭素が多く含まれた空気を体内に取り込んでしまいます。
2つの原因で酸欠状態が慢性的に続くと、体はエネルギー不足となり、様々な症状としてあらわれます。
●慢性的な片頭痛
●気分の落ち込みやイライラ
●疲れがとれにくい
●集中力の低下
●免疫が低下し風邪をひきやすくなる
酸素が充分に取り込めていないと、自覚がなくても体が勝手にストレスを感じてしまうことがあります。
ストレスは自律神経の乱れとなり、呼吸が浅くなりすいと言われています。
もともとマスクで酸欠状態の上に、ストレスでさらに酸欠になるという悪循環がおきてしまうのです。
1. 人との距離を取りマスクをこまめに外して深呼吸する
2. ストレスをためないよう、規則正しい生活を心がける
3. 鼻呼吸を意識する
マスクをつけてから体調不良を感じた人は1度「隠れ酸欠」を疑ってみてください。
対処法で症状が改善しない場合は、別の疾患のおそれがあるので医療機関へ受診しましょう。
まだまだ感染予防のためマスク生活は続きます。深呼吸をして上手に付き合っていきましょう。
提供:レイヤード
健康情報を更新しました「夏の危険な虫さされ アブ・マダニ・スズメハチ・くらげ」
今月の健康情報は夏の危険な虫さされ アブ・マダニ・スズメハチ・くらげ」です。
夏の危険な虫さされ アブ・マダニ・スズメバチ・くらげ
夏休みに入るとキャンプや海水浴を楽しむ方もいらっしゃるのでは?
夏のレジャーは虫やクラゲのトラブルも少なくありません。
刺されたときの対処法など、ご案内いたします。
湿った場所を好んで生息します。
刺されたら強い痛みがあり、患部は腫れてかゆみも強いです。
①患部の血を絞り、流水で洗い流す。
②虫刺され(抗ヒスタミン成分入り)を塗る。
③保冷剤で冷やす。
④発熱を伴ったり、数日たっても痛みがある場合は医療機関に受診しましょう。
●黒や茶色に寄ってくるので白い服を着る。
●蚊取り線香や虫よけ剤を使用。
庭や畑など身近なところにも生息します。
皮膚に吸着し数日かけて血を吸います。
痛みやかゆみはないですが、マダニの媒介による感染症に要注意です。
「重症熱性血小板減少症候群」にかかると最悪の場合は死に至るケースも。
無理に取るとマダニの一部が体内に残る危険があります。
自力で取らずに医療機関を受診しましょう。
●首、手首、足首など含め肌の露出をなくす。
●有効成分であるディートやイカリジンが含まれる虫よけ剤を使用。
巣が大きくなる7月ごろから、より活動的になります。
刺されると強烈な痛みがあります。
また毒によるアナフィラキシーショックが出ることもあります。
①ポイズンリムーバーで毒を吸い出すのが有効です。
流水で患部を吸い出すように洗い流しましょう。
②アレルギー症状が出た場合には早急に医療機関に受診しましょう。
●巣には絶対に近づかない。遭遇したら刺激せず、ゆっくりその場を離れる。
お盆の時期だけじゃなく7月の海でも十分に気をつけてください。
毒の強いクラゲに刺されたら、数分後にアナフィラキシーショックが出る可能性があります。
①こすらず、海水で洗い流す。
②手や針が残っている場合は、手袋やピンセットで取り除く。
③氷水で冷やして、必要ならば医療機関に受診しましょう。
●ラッシュガードを着用し肌の露出を避ける。
刺されると危険な虫たち、しっかり予防して夏を楽しんでください。
提供:レイヤード
健康情報を更新しました「熱中症の救急処置について」
今月の健康情報は「熱中症の救急処置について」です。
熱中症の救急処置について
梅雨の時期は、夏ほど気温はあがらないものの湿度が高く汗が蒸発しにくく体の中に熱がこもりやすくなります。
まだ暑さに慣れていないこともあり、気づかないうちに熱中症になってしまう危険性があります。
自分が気をつけることももちろんですが、
もし突然、まわりの人が熱中症になったら...
いざというときのために、対処法を確認しましょう。
●立ちくらみ
●めまい、筋肉痛
●こむら返り、大量の汗
●緊張するとお腹が痛くなる
●頭痛、吐き気、嘔吐
●倦怠感、脱力感
●集中力・判断力低下
●まっすぐ歩けない
●応答がおかしい
●けいれん、意識障害
本人の意識のある間は、
0.1~0.2%の食塩水あるいはスポーツドリンク経口補水液などを飲ませてあげましょう。
水をかけたり、濡れタオルを当てて扇ぎましょう。
氷やアイスパックがあれば、頚部、脇の下、足の付け根などの大きい血管を冷やすのも効果的です。
重症の場合は、すぐに救急車を呼びましょう。
救急車が来るまでの間は下記のような救急処置をおこないましょう。
●涼しい場所に運ぶ
●衣服をゆるめ寝かせる
●体を冷やす
●水分・塩分の補給
熱中症は重症化すると命に関わる怖い病気ですが、応急処置で助けることもできます。
おちついて、対処しましょう。
提供:メディアコンテンツファクトリー
健康情報を更新しました「その症状、もしかして過敏性腸症候群かも?!」
今月の健康情報は「その症状、もしかして過敏性腸症候群かも?!」です。
その症状、もしかして過敏性腸症候群かも?!
5月は環境の変化・気温の変化などで体調を崩しやすくなる季節です。
頻繁に腹痛に悩まされる人はいらっしゃいませんか?
今回は日本で10人に1人が発症すると言われている、過敏性腸症候群についてご案内いたします。
その名の通り腸が過敏に反応してしまう症状で、通常感じないようなごくわずかな刺激であっても腸が過敏に反応してしまい便通異常をおこしてしまう症候群です。
大腸に腫瘍や炎症がないにもかかわらず、腹痛や便通異常(下痢や便秘)、排便の回数の異常が数か月以上続くときに考えられます。
女性の方が多く、年齢とともに減っていくといわれています。
命に係わる病気ではないですが、トイレに行くことが難しい場面で強い腹痛に襲われたり、日常生活に支障をきたすこともあります。
●便通異常(下痢や便秘)が続いている
●排便をすると痛みが一時的に収まる
●急にお腹が痛くなる
●緊張するとお腹が痛くなる
●慢性的に便秘
●便秘と下痢を繰り返す
便の形状と頻度から下記4タイプに分類されます。
「下痢型」
「便秘型」
「混合型」下痢と便秘を繰り返す
「分泌型」上記いずれにも分類されないもの
重大な病気が隠れている可能性も考えられるため、検査は慎重に行います。
症状や程度、過去の病歴にあわせて大腸内視鏡検査や大腸造影検査、採血検査や検尿・検便を行います。
必要に応じて腹部超音波検査やCT検査などを行うこともあります。
残念ながら、はっきりとした原因はわかっていない過敏性腸症候群。
腸が過敏になってしまう原因は、ストレスや飲酒、不規則な生活習慣などが考えられます。
生活リズムを整え、適度な運動を心がけましょう。
またコーヒーやアルコールなどを摂取することで便通の変化が起こりやすくなることもあります。
症状を誘発しやすい食べ物がわかっている場合は、できる限り摂取を控えるようにしましょう。
もし症状がひどく、続くようであれば医療機関を受診しましょう。
提供:メディアコンテンツファクトリー
健康情報を更新しました「40歳を超えたら、特定健診を受けましょう!」
今月の健康情報は40歳を超えたら、特定健診を受けましょう!」です。
40歳を超えたら、特定健診を受けましょう!
特定健診とは、運動不足・かたよった食事・喫煙などの生活習慣が引き金となる生活習慣病の発症・重症化を予防することを目的とした健康診断です。
健康保険法に基づき40~74歳のすべての国民に対して年に一回行います。
生活習慣病とは、生活習慣が原因で起こる疾患の総称です。
●動脈硬化症
●糖尿病
●高血圧症
●脂質異常症 など
●偏った食事
●運動不足
●喫煙
●過度なストレス など
特定健診では、以下のような検査をおこないます。
病歴、服薬歴、喫煙歴など、さまざまなことを確認します。
身長や体重、BMI、腹囲の測定をします。
※BMI=ボディマス指数=身長と体重から導く肥満度を表す体格指数
身体の異常などを触診と合わせて調べます。
血圧は動脈硬化や心疾患のリスクのひとつの指標になります。
血中の脂質や血糖、肝臓の機能に関する数値を調べます。
尿中のたんぱく質量などで腎臓の機能を調べます。
このほか、心電図検査、眼底検査、貧血検査を行う場合もあります。
特定健診の結果から、生活習慣病の発症リスクが高く生活習慣の改善による生活習慣病の予防効果が多く期待できる方に対して、専門スタッフ(医師・看護師・保健師、管理栄養士など)が生活習慣を見直すサポートをします。
お勤め先やご自宅にご加入の医療保険者より案内が届きますので、案内に従い受診しましょう。
加入されている医療保険者は、お手持ちの健康保険証にて確認ができます。
主な医療保険者には下記のようなものがあります。
●健康保険組合(通称:健保組合)
●全国健康保険協会(通称:協会けんぽ)
●国民健康保険(通称:こくほ)など
特定健診を受診するには、特定健康診査受診券(受診券)が必要となります。
以下を忘れず持参しましょう。
●特定健康診査受診券
●健康保険証
※これらは加入している医療保険者から配布されます
新型コロナウイルス感染拡大防止のため家にこもりがちな生活となり、運動不足や食生活の乱れなど、生活習慣病になるリスクが高まっています。
自分は大丈夫と過信せず、年に1回は健診を受けて自分の健康状態を把握しましょう。
提供:メディアコンテンツファクトリー
健康情報を更新しました「しっかり対策をして、花粉症の時期を乗り切りましょう!」
今月の健康情報は「しっかり対策をして、花粉症の時期を乗り切りましょう!」です。
しっかり対策をして、花粉症の時期を乗り切りましょう!
今年も花粉症の季節がやってきました。
昨年に引き続き、今年も新型コロナウイルス感染症の流行と重なり、花粉症の方はなにかと気を遣うことが多いかと思います。
今回は、花粉症対策についてご案内していきます。
できれば症状が出る前から受診して予防的治療を始めると、発症を遅らせたり、症状をやわらげることができます。
症状が出てからも、内服薬、点鼻薬、点眼薬などの処方や適切な治療で症状を軽減することができます。
特に外出の予定がある日は花粉情報をチェックし、髪に花粉が付着しないよう帽子を着用し、花粉の付きやすい素材のセーターやコートなどは避け、なるべくすべすべした素材の服を選びましょう。
家に入る前に衣服や髪を払って入室し、手洗いうがいを励行しましょう。
家に持ち込んでしまった花粉を除去するため、こまめに掃除をしましょう。
以上の対策をおこない、なるべく症状が軽くすみますよう心がけましょう。
次に、コロナ禍の今だからこそ特に注意することを2つご紹介します。
鼻をかむために顔を触ったり、目がかゆくてこすったりすると手に付着したウイルスが体内に入るリスクが高まります。
こまめに手指を消毒し感染リスクを抑えましょう。
くしゃみは咳の10倍以上の距離まで飛沫が飛びます。
万が一コロナに感染していた場合の周囲の方の感染リスクを考慮し、必ずマスクを着用しましょう。
新型コロナウイルス感染症と花粉症は、くしゃみ、鼻水、鼻づまり、倦怠感など似たような症状も多く、自己判断が難しいところです。
気になる症状のある方は、早めに医療機関を受診しましょう。
提供:メディアコンテンツファクトリー